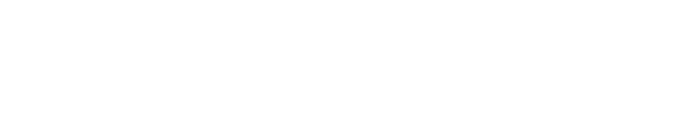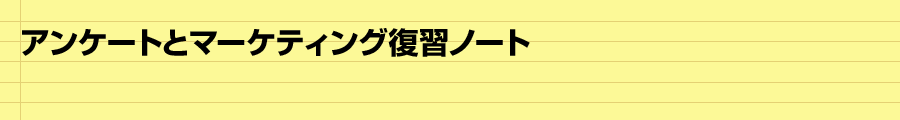H2Hマーケティング実践編
「正義とは?・その5:
公正としての正義」
ロールズは、人びとが納得できる形で社会的協働に参画するためには、何が正義で何が不正義なのか、社会の基礎構造に関する “正義の諸原理” について原初的な合意が必要だとし、正義の諸原理を考える理路について<公正としての正義>と名づけています。
まず、ロールズは「社会的協働に参画する人びとが、一堂に会して、基本的な権利と義務を割り当て、かつ社会的便益の分割を定めてくれる諸原理を選択する」という状況を想像してみようと提案します。
仮説的な状況として、ロールズは「誰も社会における自分の境遇、階級上の地位や社会的身分について知らないばかりでなく、もって生まれた資産や能力、知性、体力その他の分配・分布においてでどれほどの運・不運をこうむっているかについても知っていない」、さらに「各人の善の構想やおのおのに特有の心理的な性向も知らない」という前提条件を掲げます。
これをロールズは<無知のヴェール>(veil of ignorance)と名づけます。
この<無知のヴェール>に包まれることによって、全員が同じ条件・状況となり、特定の人を利するような判断が出来なくなります。ヴェールを取り去った時、自分が逆の立場(不利益をこうむる側)である可能性があるからです。
ロールズは「このような公正な初期状態において合意されるものが正義の諸原理であり、それが<公正としての正義>なのだ」と言います。
<公正としての正義>の下では、社会全体の利益の総量がより大きくなるという理由だけでは、それによって一部の人びとに不利益が生じても仕方がないとという合意はあり得ないと言います。
功利主義の効用原理は、相互の相対的利益を目指す平等な人びとからなる社会的協働の構想と相容れないものだ、ということです。
ロールズは<無知のヴェール>に包まれた、つまり初期状態におかれた人びとは、効用原理とは異なる2つの原理を選択するだろうと言います。
第一原理は、基本的な権利と義務を平等に割り当てることを要求する。
第二原理は、社会的・経済的な不平等(例えば富や職務権限の不平等)が正義にかなうのは、それらの不平等が結果として全員の便益(とりわけ社会で最も不遇な人びとの便益)を補正する場合に限られる。
「一部の人びとが困窮していても善の集計量が増えるならそれで相殺されるとの理由から諸制度を正当化することを、この二原理はいっさい認めない」とロールズは言い切っています。
第一原理について、ロールズは次のように説明しています。
「すべての人びとの暮らしよさ(well-being)は協働の枠組みのあり方に左右されるため、相対的利益の分け方は参加者全員(良好でない生活状態の人びとを含んだ)の心から協働を引き出すようなものでなければならない」
「(自然本性的な偶発性である)才能や資産や、(偶発性の産物に過ぎない)社会的な地位を、政治的・経済的な相対的利益を追求する上での取り引き材料に使わせないようにする」
第二原理については、「(逆に)少数の人びとがより多くの便益を稼ぎ出したとしても、そのことでそれほど幸運ではない人びとの境遇が改善されるなら、その〔分配〕状態は不正義ではない」と説明しています。
(by インディーロム 渡邉修也)