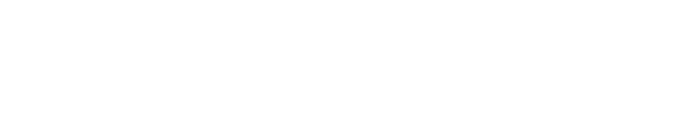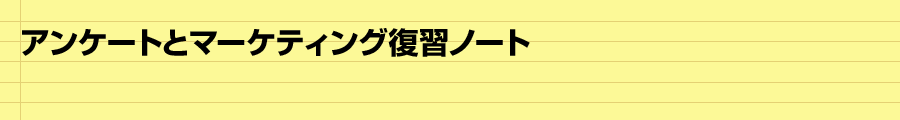H2Hマーケティング実践編
「社会的責任とブランド・アクティビズム・その10:
ソーシャル・ビジネスの運営形態」
ユヌスは、ソーシャル・ビジネスの運営形態について、次の4形態に分けることができると言っています。
- 従来型の営利企業の構造での運営
- 非営利企業の構造での運営
- 営利企業と連携する非営利企業
- 新しい事業構造
1番目の「従来型の営利企業の構造での運営」とは、事業の中心に社会的目標を据えたまま、従来型の利潤最大化企業と同じ経営原理を用いるやり方です。
この連載の中で何度か紹介したように、ユヌスは「社会的目標を掲げる営利企業は増えているが、所有者の利益追求まで放棄している企業は一握りしかない。利益を追求する企業はソーシャル・ビジネスとは言えない」と言っています。
ユヌスが考える営利企業の構造で運営されるソーシャル・ビジネスとは、利潤を最大化し持続的な運営を目指すわけですが、利益が出ても、それを所有者(株主など)に対して、当初の出資金以上に配当することはありません。
また、営利企業の構造をとるため、ソーシャル・ビジネスといっても、他の営利企業と同様に、税金を支払う義務があると言います。
社会的目標を実現のためにやっているのだから、ソーシャル・ビジネスは非課税もしくは税的優遇されても良いのではないかいう意見もあるようですが、ユヌスは「ソーシャル・ビジネスが節税のための隠れ蓑になってはいけない」と反対の立場をとっています。
2番目の「非営利企業の構造での運営」の場合は、非営利であるため、民間企業のCSRファンドから寄付が集まりやすく、財団からの助成も受けやすいというメリットがありますが、法律上、規則上の厳しい審査があり、事業内容についての制約も大きいと言います。
また、非営利の場合、所有者がいないこと、株式を発行できないことも問題があるとしています。ユヌスは「非営利よりも、営利企業の構造をとった方が、所有者は利益の配当はないものの、株を通じた所有が可能で、また株の売買や相続も可能なため、社会的目標を掲げる企業を所有しているという満足度は高い」と言います。
3番目の「営利企業と連携する非営利企業」は、ユヌスの解説によると、非営利企業が、商品やサービスを販売する営利子会社を設立し、その収益で非営利組織を運営費を確保するのは、よくある形態だということです。また同様に、営利企業とパートナーシップを結び、営利企業が収益を社会的目的の実現に充てることも多いとということです。
4番目の「新しい事業形態」とは、ユヌスのグラミン銀行のソーシャル・ビジネスの成功などを参考にして、各地で生まれた新しい事業形態になります。
ユヌスが「ソーシャル・ビジネス革命」の中で紹介しているのは、イギリスで新しい法制度として登場した「コミュニティ利益会社(CIC:Comunity Interest Company)」や、米国のロバート・ラングが考案した「低収益有限責任会社(L3C:Low-profit Limited Liability Company)」、同じく米国のコーエン・ギルバートが考案した「B法人」などです。
ここでは、これらの詳しい説明は省きますが、それぞれ社会的目標を掲げ、独自の制限やルールを設け、従来の営利企業と比べると利益の配当の割合は少ないということですが、ユヌスに言わせると、少ないとはいえ、いずれも利益の配当があるためソーシャル・ビジネスとは言い難いものだということで、利益の追求と社会的目標の追求に明確な線引きをするユヌスの「ソーシャル・ビジネス」こそが、現代資本主義の未完成の穴を埋める最善の方法だ主張しています。
(by インディーロム 渡邉修也)