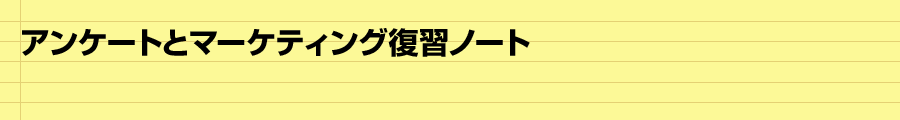マーケティング再入門
「価格設定を考えてみる・その2」
人類の歴史の中で、モノやサービスの価格は長らく売り手と買い手の丁々発止のやり取りで決められてきました。
売り手によってあらかじめ「価格設定」がされるようになったのは、19世紀後半、大量生産、大量販売の時代に入り、同じ商品を販売するのに、店員Aから買った時は500円なのに、店員Bから買ったら1,000円だったということがあると顧客の信用を失うということ、また、全ての店員が価格交渉能力に優れているわけではないということに大規模小売業者が気づいたからだそうです。
今回は、価格はいかにして設定されるべきか、ということを復習してみたいと思います。
価格設定の考え方はさまざまですが、一番最初に思いつくのは、原価(原材料費や仕入れ値)に、製造や販売にかかる手間賃や、儲け分のマージンを上乗せする「マークアップ法」と呼ばれるものです。
一見すると理に適っているように思えますが、マーケティングの教科書によると、単純なマークアップによる価格設定ではうまくいく確率は低いそうです。
需要と供給、お客様が想定していた価格と設定された価格とのギャップ、競合他社の動きなどがあり、なかなか思うようには売れてくれないようです。
「ターゲットリターン法」というものがあります。目標とする投資収益率(ROI)を生むように価格設定を行うものです。よく事業計画書などに、損益分岐点のグラフで説明されているあれですね。
販売予想数量、固定費、変動費などをもとに、8千円、9千円、1万円で販売した場合、それぞれ何千個から利益が出るようになるのか、目標とする投資収益率をもとに価格を決めていくやり方です。
しかしながら、これについても、しっかりした事前調査を行い、「この機能でこの価格であれば1万個は手堅い」といった確信が持てないのであれば、単なる紙の上での皮算用に過ぎません。
次に「知覚価値価格設定法」。このブランドであれば、これくらいの価格で当然だろうというように、お客様側にそのブランドや商品の価値を理解してもらい、記憶として定着させようとするものです。
ちなみに、知覚価値については、売場やシチュエーション、営業トークなどによってもお客様が知覚する価値の度合いは異なってきます。
百貨店などで、高価格帯の商品売場の中に、下の価格帯の売場で値引きしても売れなかった商品を混ぜて置いてみたところ、まったく値引きをしなくても売れてしまうということがあるそうです。これは「この売場で売っているものなら、品質も良いはず」という先入観と、他の高価格商品の中に混じることで「お値打ち品」に見えているのだろうと考えられます。
次回も、引き続き、価格の設定方法について復習していきます。
(by インディーロム 渡邉修也)